ブルーブラックは“色”じゃない。“出来事”──古典インクをめぐる2つの物語
お世話になっております。
ピッコロモータース工場長☆プロ道楽師のまるこフランキーです。
万年筆生活が10年以上続いてくると、なんとなく気づきますね。
「この書き味、ペンだけじゃないな」と。
で、次に興味が湧くのがインク。みなさんも、そうでしょ?
そして、色で遊ぶ楽しさに慣れてきた頃に、ふと出会うんですよ、古典インクに。
古典インクとはなにか──“色が変わる”じゃなく“色が育つ”
通称「古典インク」。 書いた瞬間はちょっと青くて、だんだん黒ずんでくる。
これは没食子(もっしょくし)インクと呼ばれるやつで、ざっくり言えば
- タンニン+鉄イオンの化学反応で発色する
- 酸化して黒ずむ=耐水性・耐光性が高い
- 紙と空気に触れることで「完成」する色
つまり、古典インクって「色」じゃなくて現象。
書いた瞬間がスタートライン。 紙の上で「色が育つ」のを見届ける──そんな観察の時間が始まるんですな。
プラチナ・ブルーブラック:背筋が伸びるインク
国産唯一の古典ブルーブラックインクを今も製造しているプラチナ。
書いた瞬間は軽やかなんだけど、乾くと「なるほど、硬派……」ってなる。
まるで昭和の履歴書。書いてるときに気が抜けない。
耐水・耐光性もピカイチで、記録性を重視する日記・ノート用途には文句なし。
ただしペン内部への定着力が高いので、洗浄はマメに。
放置プレイには向かない、ちょっと寂しがり屋なインクです。
ペリカン・ブルーブラック:変化を愉しむ、“記憶の色”
こっちは西洋の詩人って感じ。 落ち着いてるけど、たまにめっちゃ刺さる表情を見せてくる。
インクフローはなめらか。 紙によって表情がコロコロ変わるから、ノートや便箋を選ぶのが楽しい。
古典インクの中でも、「変化のグラデーション」が味わえるタイプ。
書いたあと、1時間経った文字と、翌日の文字で色が全然違う。
時間とともに沈んでいくインク。 これが、なんだか“記憶”に似てるんですよね。
注意点:古典インクはロマン。でも道具。
- 金ペン以外には入れない
- 定期的にペン内部の洗浄を必ず行う
- 極細ニブは詰まりやすいので避ける
そして、なにより僕が大事にしているのは、メーカーが古典インクを販売していない万年筆本体に古典インクを入れないこと。
つまり、プラチナとペリカンの金ペン以外には、古典インクを入れないこと。それが、トラブルを避けるリスクヘッジだと考えます。
パイロットは古典インクを出していませんからね。カスタム823なんかにいれたら、プランジャー機構の金属がどうなってしまうかはわかりません。
キャップレスに入れていたこともありましたが、どうも調子が悪く、コンバーターの中にゴミのような沈殿物が発生していたこともありました。サッと書けないキャップレスなんて…
なぜ古典インクに惹かれるのか
インクの色が変わる。
それってつまり、「今ここに書いた時間」が変わっていくってことなんですよ。
書いた直後の青、数分後の藍。そして、1日後の沈んだ深紺。
この時間差が、感情のグラデーションに重なる。
人間だってそう。
思いつきで書いた言葉が、あとになって重みを持ってくること、あるでしょう。
だから古典インクって、言葉に歴史を感じたい人に似合うんじゃないかしら。
まとめ:古典インクは「色」じゃなく「記録のしかた」
インクの話だけど、実はぜんぜんインクの話じゃない。
古典インクは、「ちゃんと書く」ことを促してくる存在です。
字を整える。気持ちを確かめる。書いたことを見返す。
──それって、全部「自己管理」なんですよ。
古典ブルーブラックは、単なる色じゃない。
あなたにとって古典インクとはなんですか?
まるこフランキーでした。ではまた。

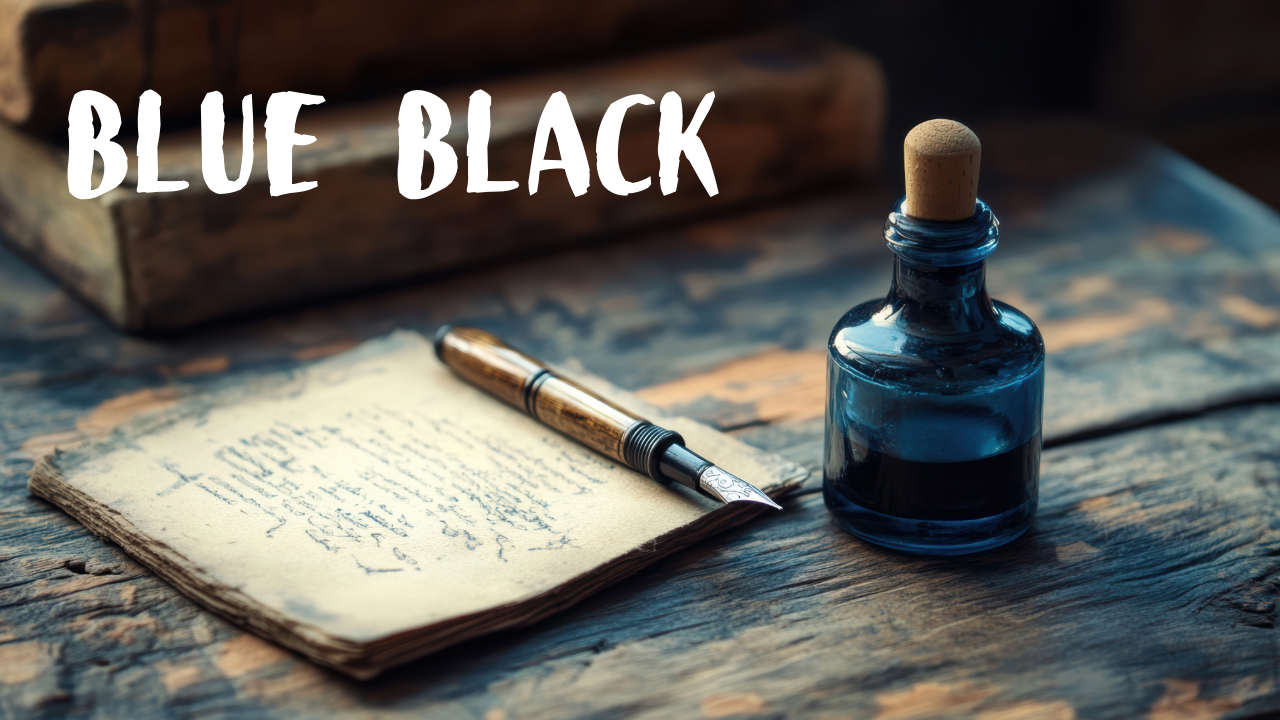
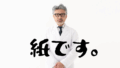

コメント