万年筆は1本でいい。問題は、紙だった|書き味の本質と道具の哲学
お世話になっております。
ピッコロモータース工場長☆プロ道楽師のまるこフランキーです。
今日は少し、僕がずっと感じていたことを話します。
それは──「万年筆は1本あれば、十分なのではないか」ということ。
もちろん、万年筆は魅力的な道具です。
書き味も見た目も、つい収集したくなる魔力がある。僕も、そうです。
けれどあるとき、ふと気づいたんです。
書き心地に満足するかどうかって、実は“紙”の問題だったのでは?と。
万年筆は“どれを選ぶか”より“どんな書き心地が好みか”が大事
国産3社のエントリーモデルで十分
万年筆の世界で「とりあえず一本持つなら?」と聞かれたら、僕はこう答えます。
「国産3社のエントリーモデルで必要十分、むしろそれがいいですよ。」と
パイロット・セーラー・プラチナの3社のペンはどれも最高。国産だから漢字を書くときの、トメ・ハネ・ハライがしっかりと表現できて、素晴らしいです。
字幅は、万年筆の良さを味わいたいのであれば、M(中字)がオススメ、手帳やノートで細かい字を書くなら、F(細字)一択。
パイロット「カスタム74」
パイロットは自動車で言ったらトヨタ、バイクで言ったらホンダ、ギターで言ったらギブソン、釣具で言ったらシマノ、当たり障りのないベーシックな性能です。
「私、みんなが使っていると言われると、急に萎えるわ。」っていう、アンチ・マジョリティなのに、結局、安牌しか引かないあなたには、パイロットが間違いない。
プリウス・ヤリス・アルファード乗りは悪いことは言わない、パイロット・カスタム74を買っとけ。(いい意味でね)
セーラー「プロフィットスタンダード」
セーラーは書き味No.1と言われている、ペン先特化型のメーカー。ガチニブと呼ばれていますが、ペン先が硬めで、スルスルとした書き味が特徴。後述するプラチナとは正反対のペン先。
特に、なんというか──「職人魂」という表現が似合う。いい意味で、ペン先だけ。あの独自のペン先から繰り広げられる書き味の濃密さ、そして全体にただよう”MADE IN JAPAN”感。
「王道の万年筆じゃイヤなのよ」とか、「書いてる瞬間をちょっと酔いたい」みたいな人には、ドンピシャです。
刺さる人には深く刺さるけど、刺さらない人には「ふーん」ってなるタイプ。バイクで言ったらスズキ。筆記具界のシュークリーム、中はとろとろ。買うときは試筆しないと絶対にダメ。
そういうクセも含めて、愛されてる。それがセーラーです。
プラチナ「#3776センチュリー」
そしてプラチナの「#3776センチュリー」僕は、1本だけ持つなら、この子かな。
センチュリーはもう──「昭和の厳格な担任教師」って感じ。
最初はちょっと硬いし、近寄りがたい。(ペン先がね)
でも、使えば使うほど「めっちゃ面倒見いいじゃん…」ってなるタイプ。
ペン先はしっかり締まってて、芯がある書き味。まるで「字をちゃんと書きなさい」って背筋を正されるような感覚。
サリサリ系なんだけど、それが気持ちいいし、ちゃんとした紙の上では、筆記時の音がスイングする。
そして何より、インクが全然乾かない「スリップシール機構」っていう、テクノロジーを積んでる。
堅物の担任教師、見た目昭和なのに中身は令和、ガラケーに見せかけて中身ギャラクシー、伊勢丹の袋みたいなエコバッグが、実はコーデュラナイロンだったみたいな。
信頼の1本を長く使いたい人には、文句なしでおすすめ。「この人だけには、ちゃんとしたい」って思わせてくれる相手。それはもう、恋ではなく、愛。
万年筆沼は、案外あっさり終わる
このあたりの金ペンエントリーモデルを、まず一本。
どれも、筆記具としての完成度は申し分ない。気張らずに書けるし、毎日使っていけるし、必要な性能はすべて揃っています。
僕が言っても説得力がないかもしれませんが、これ以上ペンを増やしても、満足度の大きな変化は望めません。あるとしても、それは“味”や“個性”の話であって、“快適さ”や“実用性”の話ではない。
書き味を左右するのは、ペンではなく紙
「このペン、カリカリする」の正体は紙かもしれない。たとえば、「この万年筆はカリカリする」「インクがにじむ」といった評価。
その多くは、実は紙との相性によって生まれているという事実に、意外と気づかれていません。
紙・インク・下敷き・環境すべてが“音色”を作る。
下敷きひとつで筆跡のニュアンスが変わるように、紙が変われば、書く行為そのものの手応えが変わる。それはもう、“音楽”に近いものです。
ギターも万年筆も、鳴りを決めるのは全体
どれだけギター本体が良くても、アンプがヘボければ音は死ぬ。
僕はこの感覚、万年筆にも言えると思っていて。
どれだけギター本体を高価なものにしても、ショボいシールドやアンプを使えば、音は途端に“軽く”なる。本体だけを磨いても、全体の鳴りは良くならない。
万年筆も同じです。
だから、紙こそが書き味の完成形。
1本の万年筆に納得しても、インクと紙と、それを支える下敷きや、机や照明、そういった環境を整えなければ、本当の“書き味”には出会えない。
なぜ僕たちは、そこまで文房具にこだわるのか
趣味だから?
たしかにそうかもしれません。けれど、それだけじゃないと思うんです。
自分を整えたい。自分を整えるための自己管理。
ただそれだけの理由で、僕らは今日も万年筆を手に取っている。
良い感情を生む道具なら、納得いくまで使いたいじゃないですか。
美しいノートに、美しい線を引いてみたい。
そうやって心を整える。それができるなら、道具にはきちんと向き合いたい。
まとめ:1本の万年筆と、紙の旅をはじめよう
これからは“紙選び”が趣味になる
ペン選びは、もう十分ではないでしょうか。
これから先は、紙との旅です。
いろんな紙に書いて、感じて、比べてみてください。
インクの出方、線のにじみ、ペン先の音。
そのひとつひとつが、自分だけの“書き味”を育てていく。
書くことそのものが、静かな贅沢になる
たった1本の万年筆を軸に、紙と向き合う時間。
それはきっと、書くことの本質に触れる、静かで贅沢な道楽です。
ではまた、どこかでお会いしましょう。
まるこフランキーでした。

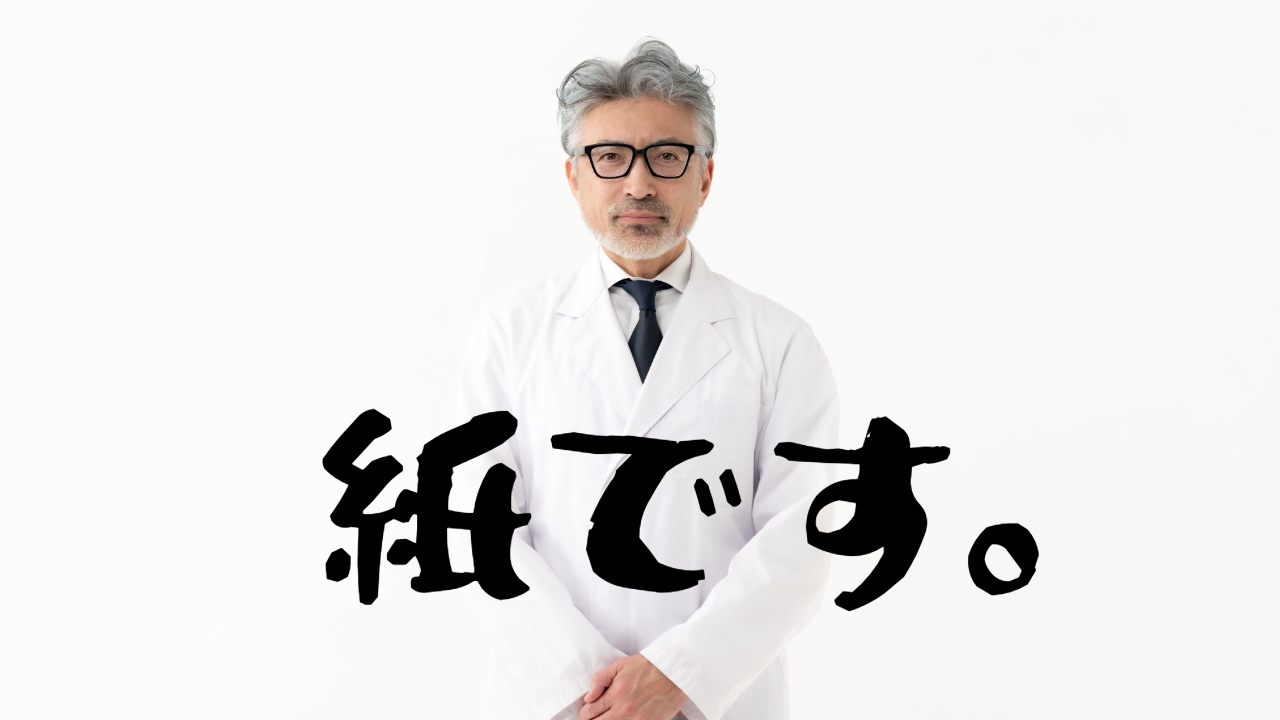
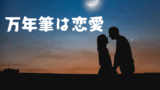


コメント