万年筆は現代の刀|太刀・打刀・脇差しの違い
お世話になっております。ピッコロモータース工場長☆プロ道楽師のまるこフランキーです。
以前、万年筆は、侍でいうところの刀である、というお話をしました。
今日はもう少し深堀りしていきたいと思います。
「武士」と「侍」は、似て非なるもの
まずちょっとだけ、歴史の話をしましょうか。
「武士」と「侍」って、同じように聞こえるけど、実は意味が違うのをご存知ですか?
武士とは:戦闘員を指し、戦闘を家業とする家系にある者を指す。
つまり、戦うために生きる人たちのことですね。野武士という言葉もあります通り、「俺は武士だ!」と勇んでいれば、とりあえずなれるものです。
現代で言うと、WEBライターのような、(といったら失礼になるかもしれませんが、僕もWEBライターですので。)今日から俺は、パソコンひとつで生きていく!と決めてしまえばなれるもの。
それが「武士」。
一方、「侍(さむらい)」は、仕える人を意味する言葉なんですね。
朝廷や貴族に仕えて、宮中の警備や身辺警護にあたったり、地方に派遣されて盗賊を追っ払ったり、内乱を鎮圧するために働いていた人たち。
「侍」は、主君のそばに控え、命をかけて仕える存在。武士でいう、刀を抜く強さはもちろんのこと、それよりも、仕える誠意に重きがある。
数学的に言うと、すべての侍は武士であるが、すべての武士が侍ではない、ということ。
このあたりの生き方の違いが、ドラマティックで面白いのです。
そして、実は武士と侍で、(もちろん時代も違うわけですが)持っている刀が違うって知っていました?
太刀(たち)

まずは「太刀(たち)」太刀はもともと、騎馬戦で使うための刀でした。
武将が馬に乗ってバッタバッタと敵を切っていくスタイル、あれが太刀です。
長くて、反りが深く、下げて佩く(はく)スタイル。
その方が騎馬上で刀を抜きやすいですからね。
※佩く(はく):腰への下げ方が、刃が下になるように紐で吊って携帯すること。面白いことに刀の展示も、腰に下げている向きで展示するそうです。つまり、画像のように、弧を描いているのが下向きなら太刀であると判断できるそうです。
時代は変遷し、太刀は儀式や正装でも佩かれ、いわば「格式」を象徴する刀として進化していきます。
打刀(うちがたな)

次に「打刀(うちがたな)」これは太刀より少し短く、腰に差して抜きやすい。
つまり、対人戦用の実戦刀です。一般的に日本刀と呼ばれているのは、打刀です。
時代的には太刀よりも新しい、侍が差しているのは打刀です。携帯の仕方は、太刀とは異なり、刃を上に向けて帯刀します。そう、文字通り帯に「帯刀」。言葉って面白いですね。
浅い反りが直線的で、徒歩での素早い抜刀・斬撃に適していて、戦国時代以降に武士の正装として定着しました。
脇差し(わきざし)

そしてもうひとつ。侍が必ず腰に差していた、もう一本の刀「脇差し(わきざし)」です。
江戸時代の武士は、腰に2振の日本刀を差していましたが、その短い方。
打刀が使えなくなった場合の、予備の武器として使用されていました。
ちなみに、江戸時代には、武士階級以外の人々にも脇差しなら所持が許されていたため、多くの名作が作られたらしいです。
3本のまとめ
ということで、まとめると
- 太刀は、走りながら切る「武力」
- 打刀は、斬らずに斬る「生き方」
- 脇差しは、己を守る「守備」
ここまで、考察していて、僕は気づきました。天才かも
これって、万年筆も同じじゃね?
太刀は、両端が丸くなっているバランス型。往年のレガシーなやつ。でかいし、太い。
打刀は、両端が平らになっているベスト型。実務で気取らずに使えるやつ。スタイリッシュ
脇差しは、ミニ万年筆。携帯用としてサッと取り出せるやつ。小さければ良いというわけではない。
そして、万年筆で刀といえば、セーラーの長刀(なぎなた)研ぎ。
練達の職人だけが作ることができる逸品です。 トメ、ハネ、ハライなどが多い漢字を最も美しく筆記するために、ペンを寝かせると太い線が書け、立てると細い線が書けるという。ほしい
僕は思いました。「道具に誇りを持てる人」は、きっと生き方にも誇りを持っているんだと思う。
だから、今は財布の中身が心許なくても、一本だけでいい。自分の刀になる万年筆を、ぜひ見つけて欲しい。僕も打刀を探す旅に出ようと思います。文房具屋さんは、僕にとって武器屋。
まるこフランキーでした。ではまた。


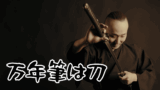


コメント